| 8. 「守りのIT経営」 と 「攻めのIT経営」 |
|
|
|
|
前ページではITシステムの種類に触れましたが、ここではそのITを使用するにあたっての活用法について考えてみます。
ITの活用法についてもいろいろな考え方があるようです。そんな中で一番分かりやすいのが「守りのIT経営」と「攻めのIT経営」とに分ける考え方でしょう。もちろん明確に分けられるほど経営活動は単純明確ではなく、実際には両方の側面を持った場合もあります。ここではいくつかのIT利用例をもとに考えていきます。
|
|
| ☆ |
|
| ● |
財務会計は守りのIT? 攻めのIT? |
|
|
例えば財務会計ソフト。普通に考えれば、その導入目的は会計事務処理の効率化と正確さの向上で、その成果として事務費用や人件費の削減が実現でき、損益計算書においては販売管理費の削減に貢献します。つまり、守りのIT経営といえます。
しかし、そこから得ることのできる迅速な会計情報を、積極的に経営戦略や業務改善に活かすことで、それは攻めのIT経営となります。
|
|
| ● |
販売管理は守りのIT? 攻めのIT? |
|
|
財務会計と並んで最も多く使われているのが販売管理ソフトでしょう。販売取引の多い会社においては必要不可欠なものです。しかし、納品書や請求書発行で終わっていませんか。単なる伝票発行マシンに留まっているケースが多いようです。たしかに、伝票発行マシンとしての利用でも販売事務の省力化にはつながります。これは守りのIT経営といえます。
しかし、もう一歩突っ込んで商品別や得意先別の販売実績や販売動向を分析することで、これからの販売計画や経営戦略に活かすことも可能です。これは攻めのIT経営となります。
|
|
| ● |
顧客管理は |
|
|
また顧客管理のIT利用も、顧客情報の整理や宛名書きのための利用であれば現状維持であり、守りのIT活用といえます。しかし、それによって得た顧客情報をもとに顧客ニーズを把握し、タイミングのよい、適切な提案や情報提供に使えば、それは売上増が期待でき、攻めのIT経営といえます。
「守りのIT経営」と「攻めのIT経営」をまとめると次のようになります。 |
|
| IT経営のタイプ |
目 的 |
内 容 |
| 守りのIT経営 |
・効率化、合理化
・生産性向上 |
●損益計算書でいうと費用を低減化すること
●限度があります |
| 攻めのIT経営 |
・顧客満足度の向上
・高付加価値化
・生産性向上 |
●損益計算書でいうと売上を増大、拡大すること
●工夫次第で無限に広がります |
|
|
|
(参考)
経済産業省などが発表しているIT経営の資料をみると、「IT利活用ステージ4つのステップ」というのが目に付きます。
第1ステージ 情報システムの導入 個人最適
第2ステージ 情報システムを部門内で活用 部門内最適
第3ステージ 部門を越えて企業内で活用 企業内最適
第4ステージ 企業を超えて最適活用 企業間最適
上記のことはある程度の規模の企業には当てはまります。しかし、規模が小さい会社においては部門最適は会社最適でもあります。また、社内最適ができていなくても業務上、企業間取引において企業間最適をやらざるを得ない場合も多くあります。大切なのは会社の実情に応じたIT化といえるでしょう。 |
|
|
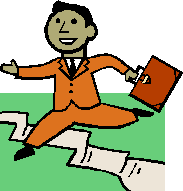 |
|
|
|
|
| ● |
処理利用と管理利用のちがい |
|
|
今日、まったくITを導入していないという会社はむしろ少数派でしょう。それなりの規模になると必然的に必要になってきます。しかし、その現状は、導入はしているものの単なる処理としての利用が多く見受けられます。
例えば、納品書や請求書の発行マシンとしての販売管理であったり、決算書を作成するだけの財務会計であったりします。せっかく販売分析や商品分析、また管理会計などの機能が備わっているのに使われていないケースの方が多いようです。つまり、管理までには至っていないケースが多いようです。
管理とは、一般に「P(プラン)→D(ドゥ)→C(チェック)→A(アクション)」、あるいは「P(プラン)→D(ドゥ)→S(シィ)」を回すことだといわれています。つまり、先ず計画し、それを実行し、実行したものを統制して見直しを図る。そして見直し改善したものを次の計画に反映させていくという訳です。
こうしてみますと、「守りのIT経営」と「攻めのIT経営」の違いは、ITシステム自体の違いなのではなく、ITを利用する側の活用法(処理と管理)の違いだともいえそうです。
|
|
![]()